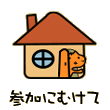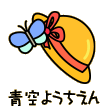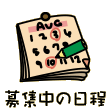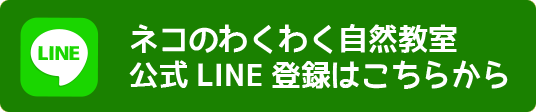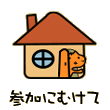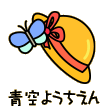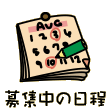|
|
 |
|
ネコのわくわく自然教室
自然教室における
感染症対策・衛生管理対策
(新型コロナ・ガイドライン) |
|
|
2020/04/11規定
2024/02/01改訂
|
|
| |
野外での自然体験活動を中心とするネコのわくわく自然教室では、さまざまな感染症や食中毒のリスク軽減を目的として、以下の対策を行っています。
自然教室での活動内容は、自分自身での制御が難しい子ども達との活動であり、時に水道や電気の無いようなアウトドア度合いの高いフィールで活動することもあり、そうした活動内での感染症対策、衛生管理は重要な項目と考えています。
プログラムごとの活動内容やフィールドによって、状況が異なるため、フィールドと活動内容ごとにルールを定めています。すべてのリスクをゼロにすることはできませんが、多段階の対策を取り決めることにより、リスク軽減を図っていることをご理解の上、参加をお願い致します。
下記対策は、専門家の対策指針を参考にして当団体で策定しています。表記している対策は、最新の情報に基づき感染予防、衛生管理精度の向上を目的として随時追加、変更する場合があります。
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
感染症・衛生管理対策
(要約版) |
重要なポントだけをまとめたものです。必ず「全文」も併せてお読み下さい。
| 1.参加条件 |
1)参加本人が、参加当日を含めて、3日以内に風邪の症状(37.5℃以上の発熱、咳、のどの痛み、倦怠感など)の体調不良がない。
2)インフルエンザ等の学校保健安全法施行規則第 18 条に指定の感染症にかかっている場合は、同規則に則り、学校への登校停止期間となっていない。 |
| 2.感染防止対策(個人) |
1)マスクの着用のルール
・調理等で規定されているときは必ずマスクを着用する。
・野外での体を動かす活動時は、熱中症や窒息などのリスクを避けるため原則としてマスクは外す。
・プログラムの集合、解散時には保護者の方にはマスクの着用は任意とする。
・体調が悪くマスクをしないといけない場合は、そもそも活動に参加しない。また帰宅をする。
・マスクを一時的に外す場合は、直接置いたり、ポケットに入れず、個別にビニール袋に入れて保管する。
・室内での活動、車内においては、必要に応じてマスクを着用する。
・マスクは不織布の使い捨てを原則とし、24時間で新しいものに交換する。
2)手洗い、消毒の徹底
・次のタイミングでは、衛生管理に則った方法での手洗い、水道が使えないときは手指の消毒をする。
(集合時、施設への入室時、トイレの後、食事・調理の前、マスク着用時、症状がある人に触れたとき、解散時)
・手洗いの際には、ハンカチを使わず、使い捨てのペーパータオルか、自然乾燥を行う。
3)事前の体調管理と検温、体調確認
・参加時には1週間前からの体調確認をします。(指定用紙に記入の上、集合時に提出)
・また日帰りでは1日1回(集合時)、宿泊では毎朝の検温を全員に行う。同時に体調の具合をスタッフが直接確認する。
4)感染予防エチケットを身につける(子ども達も身につける)
・咳やくしゃみをするときには、マスク、ティッシュ、上着の袖などで覆ってからする。手で覆うことはせず、手で受け止めた場合はすぐに手洗い、消毒を行う。
・咳などをしない場合でも、鼻や口をむやみに手で触らず、触った手で他者や共有物を触らない。 |
| 3.感染防止対策(活動) |
1)日中の活動は「野外での活動」を基本として、就寝時間以外は、野外か風通しのよいテラスや換気を行う室内で行う。
2)バスでの移動時は換気を常に行い、必要に応じてマスクを着用する。
3)野外のフィールドに出る場合も「消毒液(手指用アルコール)」をスタッフが携帯する。 |
| 4.感染防止対策(生活) |
1)室内、テントは2箇所以上の通気をして風通しのよい状態を確保。
2)コップは設置せず、水分補給は自分の水筒からのみ行う。給水ジャグは1日1回洗浄と消毒を行う。
3)感染リスクを下げるため食器洗い、水筒洗いは行わず、すべて使い捨ての食器やペットボトルを使用する。
4)調理、配ぜんは、子どもが行う場合でもマスク、手袋、ハット、使い捨てエプロンを必ず使用し、別途規定のある料理時の適切な衛生管理を行う。大皿から取り分けることはせず、個別の皿で配ぜんをする。 |
| 5.感染防止対策(施設・室内) |
1)室内に入る場合には、毎回必ず手洗いと消毒を行い、室内では必要に応じてマスクを着用する。
2)大人数での活動を終えて室内に入る際には、必ず入浴と着がえを行い、感染の持ち込みを予防する。
3)トイレはマスク、ビニール手袋、使い捨てエプロン等の適切な予防具を使用して1日1回清掃をする。 |
以上は、本団体で定めている感染症・衛生管理対策の要約版です。
必ず以下の全文をお読み下さい。 |
|
|
| |
|
|
| |
感染症・衛生管理対策
(全文) |
| 各項目の最初に表記してある内容は、日頃からネコのわくわく自然教室で取り決めている対策です。
2020年の新型コロナウイルス感染症の流行時の様な、感染症の流行時には特別な追加対応を行う場合があります。
|
|
|
| |
|
|
| |
| プログラムへの参加条件(参加者・スタッフ) |
◆参加本人が、参加当日を含めて、3日以内に風邪の症状(37.5℃以上の発熱、咳、のどの痛み、倦怠感など)の体調不良がない。
◆インフルエンザ等の学校保健安全法施行規則第 18 条に指定の感染症にかかっている場合は、同規則に則り、学校への登校停止期間となっている場合は参加できません。(例えば、インフルエンザの場合、発症後5日間かつ、解熱後3日間以上たった後の場合参加できます)
これは、保育園等での指定と同じです。
>>参考資料(保育所における感染症対策・厚生労働省)
◆必ず事前の参加承諾書に健康状態、既往症、アレルギー等の健康に関わる情報をご記入の上、事前に提出が必要になります。ご記入頂いた内容によっては、自然教室事務局から相談をさせて頂く場合があります。
>>参加承諾書(日帰り用)
>>参加承諾書(宿泊用)
>>アレルギー詳細確認書
◆宿泊プログラムでは、参加7日前から体温、体調、食欲、排便の有無をご家庭で記録し、所定の用紙にご記入の上、当日の受付時に提出をして下さい。
>>体調・クスリ確認書
|
|
|
| |
|
|
| |
| 感染症流行時の対応 |
【新型コロナウイルス等の感染症流行時】
◆プログラムの開催については、基本的に沖縄県による感染症等への警戒レベル等の要請に基づき判断していきます。
◆沖縄県、専門家によって「県内の地域間の感染予防」が必要と判断されている場合は、沖縄本島中部以外の山村部や離島への移動を自粛し、本団体の活動拠点である中城村を中心とした活動を行います。
◆事前の体調確認や感染対策の周知を徹底するため、すべてのプログラムは、事前の受付を必須とし当日の参加は不可とします。参加日までに当団体で規定している感染予防対策など読み、事前の体調確認などを所定の用紙に記入、提出が必要とします。 |
|
|
|
| |
| プログラム中の手洗い、消毒、体調確認 |
【手洗いの徹底】
◆活動中は、次のタイミングで手洗い(手首までの20秒x2回洗い)と手指の消毒をスタッフの指導の元で行います。
>>行っている手洗い方法の資料(日本食品衛生協会)
【手洗いのタイミング】
・プログラムへの集合時
・トイレ後、食事の前
・施設や車への入室時
・調理活動の前
・咳、鼻水、くしゃみをして鼻や口などを触った後
・マスク着用時
・症状があると思われる人に触れた後
・プログラムの解散時) |
◆野外活動中で水道がない場合は、手指の消毒のみを行います。
◆消毒液は「エタノール系の手指用アルコール消毒液」を使用します。消毒時は十分に手の水気を切ってから食毒液を付けることとする。
◆アルコールへのアレルギーなど特別な対応が必要な場合は手洗いのみとします。
◆手拭きはハンカチやタオルを使用せず、使い捨てのペーパータオルを使用するか、自然乾燥をします。
◆マスクを着用する場合は、次のことに注意をして、適切な使い方と廃棄の方法を心がけます。また子どもにつけさせる場合には、同様の管理方法をレクチャーします。
【マスクの着用】
◆マスクを着用する場合は、次のことに注意をして、適切な使い方と廃棄の方法を心がけます。また子どもにつけさせる場合には、同様の管理方法をレクチャーします。
◆野外での活動では、子どものマスク着用に関しては、本人が着用を嫌がり、適切な管理ができない場合は必須としません。
◆マスクの使用は、汗や雨などの水分の付着による酸欠、熱中症への影響を考慮して、野外活動中は原則として着用しないこととします。これは、マスクを付けて体を動かすことのリスクが、感染症のリスクよりも高いとの判断になります。マスクを持参している場合でも、体を動かす活動ではマスクを外すこと決まりとし、風邪を引いているなどで、マスクを着用しなければ参加できない状態の場合は、野外活動自体に参加しないこととします。
◆室内での活動では状況に応じてマスクを着用し。調理などマスク着用を規定している活動では、室内、野外問わずマスクの着用を義務づけます。
◆着用するマスクは、持参する物ではなく、衛生上の観点から原則として団体から提供する不織布の使い捨てマスク(新品)を使用することとします。1つのマスクは原則として、24時間までの使用とし、1日1回新しものに交換します。
【マスクをつけるときの注意】
◆手洗いや消毒をした清潔な手でマスクに触る
◆大人用、子ども用のサイズがあり、大人用はキッチン作業用の2層マスクと、感染予防用の3層マスクがあり使い分ける。子ども用は3層マスクのみとなる。
◆マスクの上下を確認した上で、ワイヤーの入っているノーズピースを、鼻の形に合わせて曲げて隙間がないようにする。
◆ヒダを上下に伸ばして、鼻の上、アゴの下までしっかりと覆うようにする。
◆使用中はむやみに表面を触らないようにし、息苦しいからと言って鼻の穴を外に出したりしないように注意する。
【マスクをはずすときの注意】
◆マスクの内側だけではなく、表面も汚れていると思いマスクのヒモだけを持って外していく。
◆外したマスクは、他の人に渡したり、机の上などに置いたりせず、そのままビニール袋に一度入れてゴミ箱へ捨てる。
◆一時的に外して置く場合は、1つずつ別のビニール袋に入れて、口をしばってから保管する。マスクを裸で放置しないように気をつける。
◆マスクを外すことをした場合は、必ず手洗いか手指の消毒を行う。 |
【感染予防エチケットを身につける】
◆活動の中では、感染予防のエチケットを習慣づけられるようにスタッフが指導していきます。
◆咳やくしゃみをするときには、マスク、ティッシュ、上着の袖などで覆ってからする。手で覆うことはせず、手で受け止めた場合はすぐに手洗い、消毒を行う。
◆咳などをしない場合でも、鼻や口をむやみに手で触らず、触った手で他者や共有物を触らない。
◆咳、鼻水、咽が痛いなどの症状が少しでもある場合は、すぐにマスクを着用する。
|
|
|
| |
| 施設環境、宿泊環境 |
◆室内は常に換気に努め、窓を開けサーキュレーターを使っての換気を行います。
◆空気清浄加湿器をすべての部屋に設置しています。空気循環と湿度を保つようにしています。(ネコ事務所のみ)
◆施設内には、すべての水場に手洗い石鹸、手指消毒薬、ペーパータオルを設置しています。また、嘔吐やその他の汚染があった場合への対処装備(消毒液や防護服のセット)をすぐにとれる場所に配置しています。
◆トイレは毎日清掃をし、トイレも含めた室内のドアノブ等のよく触る場所は上記の消毒液を使用して消毒を行います。
◆体調不良者が出た場合は、基本的の即帰宅となりますが、一時的に他の参加者とは離れた場所で、簡易テントを設置して休息をとります。
◆テントで宿泊をする場合は、前後の出入口を開放し(網戸に)、常に風通しが良い状態を保ちます。 |
|
|
| |
| 生活面での衛生管理 |
◆用途にかかわらず、台ふき、ぞうきん、スポンジは、0.05%の次亜塩素酸ナトリウム溶液(ハイター/ブリーチ)に30分間浸して殺菌をしてから洗濯を行います。
>>ハイターの使い方(次亜塩素酸ナトリウム溶液での消毒)
◆体調不良が見られる人の衣類等の洗濯がある場合は、他の衣類とはわけて洗い、必ず0.02%の次亜塩素酸ナトリウム溶液を洗濯洗剤に加えて使用します。(ハイター/ブリーチ)
◆嘔吐処理などで汚れた衣類、寝袋、タオルなども、同じやり方で消毒を行います。その場合は子どもが関わらず所定のスタッフが行います。その場合、使い捨て手袋、マスク、エプロン、ハットの予防具を付けたスタッフのみが行います。
◆水筒は衛生管理上使わず、すべて500~600mlのペットボトルとし、宿泊の場合は毎日新しいペットボトルを支給します。
◆給水に使う冷水やORS(経口補水液)を入れるキーパー(ジャグ/水タンク)は、1日1回洗剤洗いを行います。その際には、次亜塩素酸ナトリウム溶液(ハイター)での消毒を行います。
◆キーパー(ジャグ/水タンク)への水の補充、洗浄を行う際には、必ずスタッフが行い、マスクと消毒をした使い捨ての手袋をした上で、衛生的な環境を保ち行います。
◆バス移動を行う際は、安全に配慮した上で窓を開けて換気を良くするとともに、休憩中などにできるだけ当団体の参加者以外の人がいる人混みへ混ざらないような配慮をしていきます。夏期は熱中症予防の観点から車内でのマスク着用は行わないません。冬季は必要に応じてマスク着用とします。
|
|
|
| |
| 途中帰宅・中止について |
◆活動の途中で体調が悪くなった場合は、適切な場所での休息をとります。緊急的な処置が必要な場合は、救急搬送を要請する共に保護者への連絡を行います。
◆急を要しない場合は、その後の体調変化と既往症を考慮しながら、保護者の方と相談の上、施設やキャンプ場内での休息後のプログラムへの復帰、もしくは帰宅を検討します。
◆病院受診の際には感染の有無に関わらず、事後にネコのわくわく自然教室へご連絡をお願いしいます。
|
|
|
| |
| 料理、配ぜん時の衛生管理 |
調理、食材の準備に関しては別途定める食品衛生管理マニュアルにしたがって、スタッフ、参加者ともに衛生的な環境での調理を行います。
◆子ども達への衛生レクチャー
料理作業を行う前には、衛生管理について子ども達への注意喚起を行います。食中毒予防の3原則をレクチャーし、手洗いの方法、使い捨て手袋の脱着方法、マスクの適切な使い方を指導してから料理に入ります。
【食中毒予防の3原則】
1)つけない
食中毒の原因となる微生物やウィルスを食品につけなければ、食中毒は発生しません。
・調理をする者は手洗いをして、手袋を着用する等、清潔な手指で食材を取り扱う。
・食材を加工する器具を清潔に管理し、器具からの二次汚染を避ける。
・器具は、肉や魚など種類別に分類して使用する。もしくは洗って使う。
・原材料、半製品、製品はそれぞれ別の場所で、保管・加工し、交差汚染を防止する。
・食材は清潔に保管する。
2)増やさない
食品に付着・生存している微生物が増えなければ、食中毒は発生しない。
・食品を適切な温度帯で管理する。
・食品をなるべく常温に置かないようにする。
・計画的に作り、作り置き等は極力行わない
・食するまでの時間を考慮して、調理する。
3)やっつける
食品に付着・生存している微生物やウィルスをやっつければ食中毒は発生しません。
・非加熱の食品(サラダ等)は作り置きせずに、よく洗って提供する。
・加熱を行う場合は、中心部までしっかり加熱する。
(主な食中毒菌:75℃・1 分以上、ノロウィルス:85℃・1分以上)
・食品を取り扱う器具についても、しっかり洗う(殺菌する)。
|
◆食材管理の徹底
購入先の明確化、野菜、魚肉、生肉の分別保管、保管庫の温度や衛生状態の確認をします。
また、プログラム中の調理に関しては、不慣れな子どもがメニューを作ること、食材を管理することを考慮して、スタッフが責任を持って工程を確認します。
◆調理時の適切な装備
調理前の体調管理の徹底し、キッチン調理の際には記録を残します。またきちんとした手順に則った手洗いの徹底し、手指の消毒、使い捨て手袋、マスク、帽子の使用を子どもが料理をする際にも必ず行います。
【キッチン装備をつける手順(順番厳守)】
1)外からきたら、きれいな服に着替える
2)腕まくりをする
3)時計などを外し、髪の毛を束ねる
4)手洗いをする(手順に従い行う)
5)手指の消毒をする(水気を切ってから消毒をする)
6)キッチン用の使い捨てエプロンを着ける
7)マスクをつける(キッチン用は2層式)
8)使い捨てのキッチンハットをかぶる(髪の毛や耳が出ていないか鏡で確認)
9)使い捨て手袋をつける(手袋は手首の部分以外触らない)
10)手袋の上から消毒をする
◆適切な手洗い
手を洗う際には、マニュアルに従い手首までの30秒を2回洗いをした上で、ハンカチやタオルを使わずに自然乾燥か、使い捨てのペーパータオルで水気を拭き取った後、消毒をします。
>>行っている手洗い方法
◆適切な道具の準備
使用する用具は、保管、準備の段階から衛生管理に気をつけ、使い捨て手袋、マスク等の装備を付けて準備作業を行います。これは野外での調理でも同じです。
そのために子ども達には使い捨て手袋の正しい脱着方法を習得してもらいます。
◆作業中の衛生管理
料理中は、食材の種類によって使い捨て手袋、まな板を洗浄、もしくは交換し、食材間や作業間での交差汚染を防ぎます。肉、魚、野菜で使用するまな板、包丁を分けて使います。
◆片付けの衛生管理
使用した道具は、しっかりとマニュアルに則り洗います。卵を使用した道具は次亜塩素酸ナトリウム溶液での消毒を行い、まな板やザルは、スポンジではなくタワシを使って汚れを落とします。
>>ハイターの使い方(次亜塩素酸ナトリウム溶液での消毒)
◆肉類、卵の衛生管理
肉類や卵の衛生管理には十分に気をつけて、仕込みの段階から必ず使い捨て手袋を使い、肉類専用のバットを使います。火の通りには十分に気をつけ、スタッフが必ず確認し生の状態で出さないようにします。
また、必要に応じて事前に蒸したり茹でたりをする対策を行います。
◆配ぜん時の対応
配ぜんは子どもが行う場合でも、手洗いの上、使い捨て手袋、マスク、エプロン、ハットを装着して行います。
また、配ぜんは特定の担当者を決めて、関わる人を限定します。
配ぜんは個人の皿へよそい、大皿でとる形式はしません。
おかわりを行う際には、必ずキッチン担当のスタッフが配ぜんを行い、お玉などがお皿に接触しないように気をつけてよそいます。お皿ごとに手袋を消毒します。
◆使い捨て食器の使用
食事は基本的に使い捨ての食器(天然素材を主成分にしたものを使用)、子どもが行う食器洗いによる感染リスク軽減をはかります。
(使用する製品の主原料)
・平皿…バガス材(さとうきび)を主原料にした製品
・深皿…紙パルプを主原料にした製品
・箸、スプーン…白樺等の無漂白の木材を主原料にした製品
・弁当箱…とうもろこし由来のコンスターチを主原料にした製品
◆とりわけの方法
口をつけた後の料理を他の子やスタッフに再分配することは禁止し、好き嫌いや分量の調整などは、食べ始める前に行います。その際も子ども自身が行わず、必ずスタッフが行います。
◆調理中のケガへの対応
1)調理中に指先を包丁で切るなどの怪我をした場合は、すみやかに応急処置の手順にのっとり止血処置をおこないます。
2)止血は清潔なガーゼやペーパータオルを使い直接圧迫でおこなう。(ひどい傷でない場合は本人に押さえてもらう)直接圧迫は15〜30分継続し、その間は調理エリアの外で座って待機します。
3)手の怪我をした人は、原則として調理に関わることはできませんが、使い捨ての手袋を着用すれば調理に加わることができます。絆創膏の手でそのまま調理をすることはしないように注意します。
4)怪我をした人が使っていた調理道具は、他の機材とわけて洗い、清潔なタオルで水ぶきをした上で消毒液を使って消毒する。その際に使ったスポンジは、次亜塩素酸ナトリウム溶液での消毒をします。
5)怪我をした時に扱っていた食材は、そのとき触れていたり、血が付いていたものをビニール袋に入れて廃棄し、洗って使い回すことはしないようにします。
◆関わるスタッフは、応急処置の資格取得を行っています。
>>Medic FirstAidチャイルドケアプラス
◆衛生的な対処をするための用具準備
調理作業時には、施設内、キャンプ場を問わず、以下のものをすぐに取れる場所に配置しておき、常に清潔に保つ様に管理しています。
・使い捨てエプロン(白色など明るい色、黒や紺色などの汚れの見えにくい色の濃い物は不可)
・ヘヤキャップ(キッチン内で被る使い捨ての帽子)ない場合は三角巾、バンダナで代用
・マスク(使い捨て)
・ビニール手袋(バリア)
・ペーパータオル(手ふき用)
・手指用消毒薬
・生ゴミネット
・ビニール袋(5斤袋、2斤袋)
・食器洗い用洗剤
・スプレー式塩素系消毒薬(ハイター)
・清潔なふきん(台ふき)
・清潔なタオル(食器等を拭き取るタオル)
また次のものはキッチン外のわかりやすい場所に置き、必要なときにすぐに取れるようにしておきます。
・救急用具(ファーストエイドキット)
・ティッシュ
・ゴミ袋(ゴミ箱用)
キッチンへ電話の子機、携帯電話、トランシーバーを持ち込み使用する際には、必ずビニール袋につつみ汚れが手と機材相互に付かないようにします。
|
|
|
| |
|
|
| |
新型コロナウイルス感染症に関する対策は、感染症の専門家(沖縄県立中部病院感染症内科 高山義浩先生)のアドバイス等を参考にして策定しています。
それでも、子供たちが集まるイベントにおいて、新型コロナウイルス等への感染を完全に防ぎきれるものではありません。持病のあるお子さんなど、とくに感染が心配な方については、参加を見送られることをお勧めします。
これらの対策内容は、これらは最新の情報に基づき、感染予防と衛生管理の向上を目的として追加、変更していくことがあります。 |
|
|
| |
|
|
| |
感染対策改訂履歴
▼一部改訂 2024/02/01
コロナ禍の収束の状況を見ながらの条件緩和と整理。
(主な改訂項目)
◆コロナ特記の削除(一部を通常のルールに統合)
▼一部改訂 2023/04/01
コロナ禍の収束の状況を見ながらの条件緩和と整理。
(主な改訂項目)
◆参加条件の整理
◆マスク着用等の整理
▼一部改訂 2022/03/07
感染状況や変異株の動向、国や県の指針変更、専門家の意見を踏まえて、一部改訂をしています。
(主な改訂項目)
◆濃厚接触等による参加制限日数の変更(14日→7日)
◆沖縄県外渡航歴によるの参加制限の変更
▼一部改訂 2021/04/15
まん延防止等重点措置の施行動向を踏まえて、一部改訂をしています。
(主な改訂項目)
◆沖縄県外からの参加制限にまん延防止等重点措置が発せられている都道府県を追加
▼一部改訂 2021/03/10
緊急事態宣言の動向を踏まえて、一部改訂をしています。
(主な改訂項目)
◆沖縄県外からの参加制限を緊急事態宣言下の都道府県に変更
▼一部改訂 2020/12/15
全国的な動向を踏まえて、沖縄県内に在住の方に限定した参加に改訂。
(主な改訂項目)
◆沖縄県外からの参加、県外への渡航歴に対する制限の追加。
◆マスク着用についての厳格化(室内・車内は常時、不織布に限定し、毎日新品を使用)
▼一部改訂 2020/09/15
沖縄県内での感染状況の落ち着きを受け、感染症専門医のアドバイスを元に、一部ガイドラインを改訂しました。
(主な改訂項目)
◆沖縄県外からの参加、県外への渡航歴に対する制限の削除
◆開催条件の表記の修正(現在の県による警戒レベルに表現を合わせる)
▼一部改訂 2020/07/23
沖縄県内での感染状況の拡大を受け、感染症専門医の指導の下に、一部ガイドラインを改訂しています。
(主な改訂項目)
◆沖縄県外からの参加、県外への渡航歴に対する制限の追加
◆お子さんが通っている学校で感染が確認された場合の対応
|
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
ご質問は公式LINEからお願いします。 |
|
| |
|
|
| |
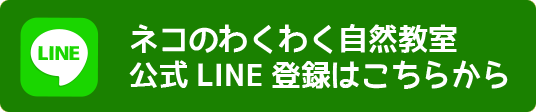 |
|
 |
|
 |